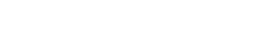FAQ
依頼関連
- どのように依頼すればよいですか。
こちら(分析試験のご依頼の流れ)をご覧ください。検体の送付にあたっては、検体到着日が弊財団の営業日となるようお送りください。
- 検体の送付先を教えてください。
最寄りの事業所(検体送付先 一覧)へご送付ください。
- 営業日・営業時間を教えて下さい。
土曜、日曜及び祝日は休業日となります。年末年始は12月30日から1月4日まで休業いたします。なお、ゴールデンウイーク,お盆の期間は、暦通り営業いたします。
電話でのお問い合わせは、平日の午前10時から午後4時まで承っております。分析ナビ@jfrlサービス総合サイトのお問い合わせもご活用ください。窓口でのご相談については、事前のご連絡をお願いします。
- 分析料金はどのくらいかかりますか。
分析料金はサービスの各カテゴリーページに掲載しております。掲載がない分析項目につきましては、お問い合わせをお願いします。
- 時間はどのくらいかかりますか。
分析項目によりますが、一般的には約2~3週間かかります。至急対応(料金は通常料金の5割増し) も可能ですので、日程調整をご希望の場合は、お問い合わせください。
- 分析を依頼したいのですが、事前に予約は必要ですか。
ご依頼内容が決まっている場合、予約は不要です。ただし,試験条件に特別な指定がある場合や事前相談をご希望の場合は、お問い合わせください。
- どんな分析をすればよいか相談に乗ってもらえますか?
ご依頼の目的に応じた分析項目や試験方法の選択について、ご相談を承ります。お客様のニーズに合わせた最適な分析をご提案いたしますので、お問い合わせください。
- 取扱いができない検体はありますか。
検体が、人、設備、施設及び輸送等に対して危険性を有する場合には、受託に応じられないことがありますのであらかじめご相談ください。輸送に関しての危険性についてはこちらのご案内も合わせてご確認ください。
また、貴社製品以外の商品が検体の場合も、あらかじめご相談ください。
- 依頼時に使用する容器の貸し出しは行っていますか。
水質試験の場合、試験内容によって使用する容器が異なります。適切な容器の貸し出しも承っております。詳しくは、お問い合わせください。
- 分析が終わったら検体は返してもらえるのですか。
特にご希望がない限り、検体は返却いたしません。返却をご希望の場合は、ご依頼時にお申し付けください。ご返却検体は着払いの宅配便でお送りいたします。分析終了後時間が経ちますと、返却のご希望に添えない場合がございます。なお、検体が輸送に制限のある危険物等の場合は別途ご相談ください。
- 料金はどのように支払うのですか。
試験検査料金が確定しましたら、ご請求書を発行いたしますので、お早めに指定銀行口座へのご入金をお願いいたします。
- 分析結果はどのように受け取るのですか。
分析試験成績書等はPDFファイル形式で分析ナビ@jfrl 分析依頼関連サイト上にご提供いたします。印刷物をご希望の場合は追加で有料にて承ります。
- 成績書をメールでもらえますか。
セキュリティ―を考慮し、メールでの送信は行っておりません。
PDFファイル形式の成績書がダウンロードできる「分析ナビ@jfrl 分析依頼関連サイト」をご利用ください。ご利用に関しましては、こちらをご参照ください。
- 成績書に試験方法は記載されますか。
試験方法や法令名(法律に基づく試験の場合)を記載いたします。なお、お客様から試験法や結果表記等について特別なご指示をいただいた場合は「依頼者指定の方法によった」という旨を記載させていただく場合がございます。
- 試験方法の概要は教えてもらえますか。
簡易フローチャートをサービスの各カテゴリーページ内に掲載している項目もございます。各項目の詳細(▼をクリック)の分析方法をご確認ください。
- 分析結果は英文でもらえますか。
英文の成績書又は報告書は、ご依頼時又は和文成績書等の発行後1年未満の場合のご要望に対応いたします。料金についてはお問い合わせください。会社名、検体名の英名が必要になりますので『英文成績書に関する記載事項』に必要事項をご記入いただき、ご送付ください。なお、英文成績書発行のお申し込みは、分析試験ご依頼のお客様に限らせていただきます。
英文成績書依頼に関する記載事項
PDF版はこちら
エクセル版はこちら和文成績書をお持ちの場合は、専用フォームからもお申込みいただけます。
- 同じ成績書をもう何通かほしいのですが。
分析ナビ@jfrl 分析依頼関連サイト上に掲載されているPDFファイル形式の成績書は、閲覧可能期間内でしたら何回でもダウンロードできます。
郵送で成績書の印刷物をお受け取りの場合、発行日から5年以内に限り有料での追加発行が可能です。詳細についてはお問い合わせください。
なお、追加発行のお申し込みは、分析試験をご依頼いただいたお客様に限らせていただきます。
- 成績書の検体名を変更してほしいのですが。
成績書発行後は、検体名や依頼者名等の記載事項を変更することができません。
分析ナビ@jfrl 分析依頼関連サイトのお申し込み画面または分析試験依頼書にお間違いのないように入力・記入をお願いします。なお、ご依頼の時点で正式な検体名が決まっていない場合には、事前にご相談ください。
- パッケージに分析結果を掲載したいのですが、どうしたらよいですか。
弊財団の名前を記載される場合は、お客様の責任において掲載して下さい。なお、関係法令がある場合はこれに従い、また第三者の誤解を招かないようお願いいたします。弊財団約款第10条にも記載しておりますので、ご参照ください。
分析ナビ関連 サービス総合サイト
- 2026年2月のリニューアルで分析ナビはどのように変わったのですか。「分析ナビ@jfrl サービス総合サイト」とはなんですか。
分析ナビ@jfrlは新たに「サービス総合サイト」が開設され,2つのサイトで構成されます。これまで通り、無料でご利用いただけます。
①「サービス総合サイト」は、分析試験などのご相談・問合せができ、その履歴管理ができます。
②「分析依頼関連サイト」は、分析試験のお申し込み、分析試験成績書(結果)・請求書等のダウンロード・依頼履歴管理ができます。サービス総合サイトとは別にユーザ登録が必要になります。
※従来(2026年2月1日まで)の「分析ナビ@jfrl」は、「分析ナビ@jfrl 分析依頼関連サイト」へ名称を変更しました。従来の「分析ナビ@jfrl」をご利用のお客様は、同じIDで「サービス総合サイト」をご利用いただけます。
- リニューアル前の「分析ナビ」のユーザーIDは使用できなくなりますか。
従来のサービス「分析ナビ@jfrl」をご利用のお客様は同じIDを使用して「サービス総合サイト」をご利用できます。
※従来(2026年2月1日まで)の「分析ナビ@jfrl」は、「分析ナビ@jfrl 分析依頼関連サイト」へ名称を変更しました。「分析依頼関連サイト」は、分析試験のお申し込み・分析試験成績書(結果)・請求書等のダウンロード・依頼履歴管理ができます。サービス総合サイトとは別にユーザ登録が必要になります。
- 問い合わせの仕方を教えてください。
お問い合わせはこちら(分析ナビ@jfrlサービス総合サイト)からお願いします。
ユーザIDの取得が必要になりますので、「新規ユーザ登録」より登録申請をお願いします。
ログイン画面の「新規ユーザ登録」より登録していただきますと、ユーザID発行のメールが届きますので、パスワードを設定し、ログインしてください。
- IDやパスワードを忘れてしまいました。
ログイン画面の「IDを忘れた場合」または「パスワードを忘れた場合」のリンクからお手続きください 。
ID忘れ: 本人確認のため、ご案内までにお時間をいただく場合があります 。
パスワード: 再設定用メールが送信されます 。※「分析依頼関連サイト」のパスワードとは異なりますのでご注意ください 。
- ログインIDの有効期限はありますか。
本サイト(サービス総合サイト)のIDに有効期限はありません 。 連携する「分析依頼関連サイト」については、1年の有効期限が設定されています 。ただし、ログインするたびに期限はその日から1年後に自動延長されます。
- サービス総合サイトからではなく、分析依頼関連サイトから直接ユーザー登録申請をしました。サービス総合サイトを使用する場合は,別に登録が必要ですか?
個別の登録は不要です。
「分析依頼関連サイト」のID(アルファベット3文字+数字3桁)と「サービス総合サイト」のIDは共通でログイン可能です。
「分析依頼関連サイト」ご登録時に「サービス総合サイト」ユーザー様としても自動的に登録されます。
なお、パスワードはそれぞれ個別に設定が必要です。「分析依頼関連サイト」の「ユーザー登録完了のお知らせ」メールとは別に「サービス総合サイト」の「パスワード設定のお願い」依頼メールが送信されますので、パスワードの設定をお願いいたします。
- サービス総合サイトのIDを持っていれば、そのまま分析依頼関連サイトで申し込みができますか?(「分析依頼関連サイト」を利用したいが,「分析依頼関連サイト」のボタンがグレーアウトして押せません。)
別途、分析依頼関連サイトの利用登録(アカウント作成)が必要です。
サービス総合サイトにログイン後、ホーム画面右下のLink集にある「分析依頼関連サイトの登録」からお手続きをお願いします。
登録完了後は、サービス総合サイトから分析依頼関連サイトへスムーズに移動して、分析の申し込みができるようになります。
- ユーザー登録をしないと問い合わせができないのですか。
お問い合わせには分析ナビ@jfrlサービス総合サイトのユーザ登録が必要になります。
- どのように問い合わせをしたらよいですか。
「お問い合わせ」ボタンよりお問い合わせください。
「医薬品・医療機器」か「食品・添加物、ペットフード、化粧品、その他」で、お問い合わせ先が分かれています。検体種に応じてご選択ください。
- 資料や画像を添付して問い合わせすることはできますか。
はい、可能です。入力画面の下にある「ファイルをアップロード」から添付してください。
複数のファイルを送りたい場合はZIP形式で1つのファイルにまとめてください。
ファイルを削除・変更したい場合は、お手数ですが最初からお問い合わせをやり直してください。
- 送信した問い合わせ内容の確認や追記はどうすればよいですか。
「お問合せ履歴」から該当の「問い合わせNo.」→「問い合わせ詳細No.」をクリックすると、内容を確認できます。
問い合わせに対する回答は,「JFRL回答欄」で確認してください。
追加の連絡事項や問い合わせは「顧客回答欄」に入力してください。
詳しくは【JFRL】サイト利用マニュアル_05_お問い合わせ確認1.1 1.2をご参照ください。
- 相談が終わったので、分析を申し込みたいです。
分析依頼のお申し込みは、本サイトではなく「分析依頼関連サイト」で行います 。 ホーム画面のLinkから「分析依頼関連サイト」に移動してお申込み手続きをお願いいたします。
「分析依頼関連サイト」の基本操作についてはこちら(分析依頼関連サイト利用マニュアル)をご覧ください。
本サイトの「問い合わせNo.」を備考欄に記載いただくと手続きがスムーズです 。
- 問い合わせ内容を社内のメンバーと共有できますか。
「サービス総合サイト」は個別のマイページで構成されるため,社内の別のご担当者様とは共有ができません。
ただし,「分析依頼関連サイト」では,ご依頼情報(進捗や結果)については,共有が可能です。詳しくは分析依頼関連サイトのFAQ,依頼状況等の情報を社内で共有することはできますか。[ナビFAQ共通]をご確認ください。
- 見積書が欲しいのですが、どうすればよいですか。
「サービス総合サイト」のお問合せ時にお見積書のご希望をご連絡ください。
医薬品・医療機器の場合、「セルフ見積」「正式見積」もご利用いただけます。
「分析依頼関連サイト」から見積のご依頼も可能です。「分析依頼関連サイト」の基本操作についてはこちら(分析依頼関連サイト利用マニュアル)をご覧ください。
- 「セルフ見積」画面で検索をしたところ、「該当する規格/各条が見つかりません」と出ました。どうしたらよいですか。
ホーム画面の「お問い合わせ」ボタンよりお問い合わせください。
分析ナビ関連 分析依頼関連サイト
- 分析依頼関連サイトに登録すると、分析ナビ(Web)からしか申込みができなくなるのでしょうか。今まで通り紙の依頼書を使って申込んでも大丈夫でしょうか。[ナビFAQ共通]
分析試験のお申込みは、分析ナビ@jfrl 分析依頼関連サイトまたは依頼書(紙)をご利用ください。
こちら(分析試験のご依頼の流れ)をご覧ください
- 使い方を教えてください。[ナビFAQ共通]
基本操作についてはこちら(分析依頼関連サイト利用マニュアル)をご覧ください。
- 分析依頼関連サイトから受託可能な項目すべてが閲覧、選択できますか。
すべてを見ることはできません。ご希望項目が無ければ「ご希望の項目が見つからない場合」を選択し、検体情報の注意事項欄でご希望の項目をお知らせください。
- パソコンを変えるとログインできなくなることはありますか。
ご利用コースによって異なります。
• ID認証コース: どのパソコンからでもログイン可能です。
• 電子認証コース: 電子証明書をインストールしたパソコンのみで利用可能です。パソコン変更時は証明書の再インストールが必要です。
※分析ナビ@jfrlのご利用環境はWindows のMicrosoft Edge及びGoogle Chromeです。
- 依頼状況等の情報を社内で共有することはできますか。[ナビFAQ共通]
グループ化で情報の共有が可能です。
グループメンバー全員が分析ナビユーザ、かつ同じ会社内であれば、メンバーをグループ化することにより依頼状況や成績書等の情報を共有することができます。
グループ化のお申込みは以下のURLより申請書をダウンロードいただき、必要事項をご記入後、分析ナビ@jfrl サービス総合サイトのお問合せボタンより送信ください。
■各種申請書ダウンロード:https://www.jfrl.or.jp/fountain/download
お願い:グループ化は、全てのメンバーが分析ナビのログインIDを取得した後にお申込みください。
- ご利用コース(ID認証・電子認証)の違いは何ですか。
ID認証:IDとパスワードがあればどのパソコンからもご利用いただけます。
電子認証:電子証明書をインストールしたパソコンからのみご利用いただけます。
各ご利用コースの特徴についてはこちらをご覧ください。
- 結果が見らません。
ご登録の認証方式をご確認ください。「電子認証方式」と「ID認証方式」ではログインするURLが異なります。
電子認証方式でログインができず,エラーコードが表示される場合は,表示された番号を「お問合せ」ボタンからお知らせください。エラーに関する詳細は下記をご覧ください。 https://www.jfrl.or.jp/fountain/error
- 成績書発行のメールにあるURLからログインしようとしてもエラーになります。
サービス総合サイトのパスワードを入力していないかご確認ください。分析依頼関連サイト専用のパスワードが必要です。お忘れの場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れの方はこちら」からお手続きください。
- 分析ナビで見積もりはもらえますか。[ナビFAQ共通]
分析依頼関連サイトからお見積りの依頼ができます。必要事項を入力いただき、最後の画面(Step3)で見積りの依頼ボタンを押すことで、選んだ項目について見積書の申請ができます。見積書は後日、分析依頼関連サイト上に掲載いたします。
なお、項目選択画面(Step1)では弊財団が受託できる主な項目について、標準単価を確認することができます。
- 「分析依頼関連サイト」に登録しようとしたところ、有効期限切れと表示されて、登録ができません。
ホーム画面の「お問合せ」ボタンよりお問い合わせください。
- 「分析依頼関連サイト」の登録内容変更やその他の詳しいFAQはありますか。
登録内容の変更は「分析ナビ@jfrl登録変更」からご確認ください。その他の詳しい使い方等はこちらからご確認ください。
- 分析前の相談や見積りについて問い合わせしたい場合はどうすればよいですか。
「サービス総合サイト」からお問い合わせください 。
ホーム画面の「お問い合わせメニュー」から、検体の種類(食品・添加物・化粧品等、または医薬品・医療機器)を選択して入力フォームへお進みください。
- 試験結果や成績書の内容について質問したい場合はどうすればよいですか。
分析依頼関連サイトの「お問合せ」から該当の受付番号を指定してお問い合わせください。
栄養成分表示関連
- 栄養成分表示の対象と表示義務の成分を教えてください。
食品表示基準では「原則として全ての一般用加工食品及び一般用添加物に栄養成分表示を義務付ける。」とあります。
表示が義務付けられる栄養成分等は、エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量(ナトリウム)です。ナトリウム塩の添加が無い食品は「ナトリウム」の表記が可能ですが、この場合も食塩相当量の併記は必要です。
その他の栄養成分であるミネラル、ビタミン等の表示は任意となりますが、今回新たに表示が推奨される成分として、飽和脂肪酸と食物繊維が挙げられています。これは国民の摂取状況、生活習慣病との関連等の観点から消費者における表示の必要性が高いと考えられ、将来的な表示義務化を見据えてその他の任意表示成分より優先度が高いものとして規定されています。
また、生鮮食品にも栄養表示が可能ですが、その場合も加工食品に準じて食品表示基準のルールに従った表示が必要です。
詳しくは消費者庁HPもご確認ください。
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)
- エネルギー(熱量)はどのようにして求めるのですか。
食品表示基準では、修正アトウォーター法を用いて計算します。基本的には、たんぱく質(4 kcal/g)、脂質(9 kcal/g)、炭水化物(4 kcal/g)のエネルギー換算係数を乗じ、その総和がエネルギーとなります。他に食物繊維(2 kcal/g)、アルコール(7 kcal/g)、有機酸(3 kcal/g)などは特定のエネルギー換算係数を用いることができます。さらに食品表示基準ではオリゴ糖などの難消化性糖質について個別に定められたエネルギー換算係数を用いる場合があります。
一方、食品素材としての野菜や穀類、肉類 等については、日本食品標準成分表(以下、成分表と略記)に掲載されているエネルギー換算係数を用いた算出が一般的です。なお食品表示基準では生鮮食品に栄養表示をすることも可能ですが(任意)、その場合は修正アトウォーター法によるエネルギー(熱量)の算出が必要です。
- たんぱく質、脂質、炭水化物に量りこまれる成分への対応は?
食品表示基準で定められた分析方法では、対象とする成分の他にも様々な成分を一緒に測り込むことがあります。
これまでも、お茶やコーヒー、ココアなどに含まれるカフェイン、テオブロミンに由来する窒素がたんぱく質の測定値(窒素含量からの換算)に影響を与えるため、これらを差し引き補正することがありました。食品表示基準では、これらに加えて、窒素を含む人工甘味料(アセスルファムカリウムやアスパルテームなど)に関して、これらに由来する窒素を全窒素から差し引くことが可能となりました。更に脂溶性ビタミンが脂質に含まれてしまう点や、水溶性ビタミンが炭水化物に含まれてしまう点も、各々を別途測定し、得られた値を差し引くことで脂質や炭水化物を過大評価しない手法を取ることも許容されました。
弊財団では、従前のお茶やコーヒー、ココアに含まれるカフェインなどに加え、人工甘味料や、ビタミンを高含量に含む健康食品などを対象とし、たんぱく質、脂質、炭水化物に影響する成分を考慮したエネルギー等の計算が可能です。
- 炭水化物や糖質は計算とありますが、どのようにして求めるのですか。また、食物繊維との関係はどうなりますか。 加えて、表示上の注意点がありますか?
食品全体を100%(100g/100g)と考え、水分、たんぱく質、脂質、灰分の割合(g/100g)を差し引き、残りを炭水化物とします。また、炭水化物の中を更に「食物繊維」と「糖質」に分けることができます。計算式は以下のようになります。
100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)=炭水化物
100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分+食物繊維)=糖質
したがって、炭水化物=糖質+食物繊維 ともいえます。なお、食品表示基準施行により、「糖質+食物繊維」で表示する場合にも炭水化物の併記が必須となりました。栄養表示基準では不要でしたので大きな変更点となります。
- 栄養成分表示を目的に食物繊維を依頼する場合、どの試験方法を選べばよいですか?
食物繊維は試験方法の原理により,①不溶性食物繊維,②高分子水溶性食物繊維及び③低分子水溶性食物繊維の3つの画分に分類できます。
また,食物繊維の試験方法はいくつかありますが,それぞれ定量できる食物繊維の測定対象が異なるため,同じサンプルでも,試験方法により,分析値も異なる場合があります。そのため,測定対象と目的(栄養成分表示するため,など)に合わせた方法の選択が必要です。こちらに簡易的にまとめましたので,ご参照ください。
- 食塩相当量はどのように求めるのですか。
食塩相当量はナトリウムの量を測定し、2.54を乗じて算出します。食塩(塩化ナトリウム)そのものは直接測定できませんので、その中のナトリウムを測定し、食塩に相当する量を計算で求めるという方法です。
この方法では食塩以外の形態のナトリウムも食塩として計算されることになります。そのため、『食塩』ではなく『食塩相当量』という表現になっています。
- 食品表示基準と日本食品標準成分表の相違点を教えてください。どちらの方法で依頼したらよいですか。
食品表示基準と日本食品標準成分表(以下成分表)では多くの同様の試験手法が定められていますが、エネルギー(熱量)の計算方法(Q2-3参照)や試験法の詳細では若干の相違があります。
栄養成分表示をする目的の場合は食品表示基準に準じた試験法を適用することが望ましいと考えられます。一方、成分表は給食等、調理食品の栄養成分の計算に使用するなど、食材の栄養成分を収載するということを主目的として作成されています。食材等、成分表の数値と比較することが目的の場合は、成分表に準じた試験手法を用いることをお勧めします。
なお、栄養成分表示には分析値ではなく、計算値などを用いた『推定値』での表示も可能となっており、そのデーターベースとしての成分表の役割が期待されています。食品表示基準で定められた試験法は成分表との整合をとることが一つの目的として改訂されています。
- 栄養成分について表示する食品単位当たり(例:100ml当たり,1袋当たり,1粒当たり)で結果を提出してもらえますか。
ご提出可能です。100gあたりの試験結果,重量または比重の結果を用いて算出致します。
そのため,各種栄養成分分析に加えて,重量や比重のご依頼が必要です。ただし,重量については,お申し出の表示する食品単位の数値を用いて算出することも可能です(有料)。
- 栄養成分(水分、たんぱく質、脂質、灰分)の結果「0.1g/100g未満」とは何ですか。
検体100g当たりの成分量が0.1g未満であることを表しております。栄養成分を表示する際は「0(ゼロ)」と表示できます
ビタミン関連
- ビタミンAをIU単位で表記できますか。
1 IU=0.3μg レチノールの関係ですが、食品表示基準ではIUは表示できないことになっています。
- ビタミンAはレチノール、カロテン、クリプトキサンチンのどれを分析したらよいですか。
レチノールは動物性食品に含まれており、カロテン・クリプトキサンチンは主に植物に含まれています。これを基に分析対象を判断します。
ただしクリプトキサンチンは含まれている植物が限られていますので、比較的含量が高い柑橘類、柿、パパイヤ、とうもろこし,鶏卵等では分析をお勧めします。
- ビタミンKはビタミンK1とビタミンK2の両方を分析したほうがよいですか。
フィロキノン(ビタミンK1)は主に植物に含まれています。メナキノン類(ビタミンK2)は動物性食品に含まれています。含有しているビタミンKの種類がわかっている場合はそれだけを分析をすればいいですが、不明であればフィロキノン(ビタミンK1)と一般的なビタミンK2であるメナキノン-4の両方を分析することをお勧めします。メナキノン-7は納豆などの発酵食品に多く含まれています。
微生物関連試験
- 食品の一般細菌数(生菌数)を測定するのはなぜですか。何が測れるのですか。
一般細菌数(生菌数)の測定は食品の安全性、保存性、衛生的取扱いの良否、環境の清浄度等を評価する一つの指標となります。発酵食品等一部の食品を除き、 一般細菌数が高い食品は製造、加工、輸送、貯蔵工程での不備や非衛生的取扱いのあったことや、温度管理が不適切であったことが推測されます。
弊財団では、標準寒天培地を用い、35℃、48時間培養して生育したコロニー(集落)の数を計測し、一般細菌数(生菌数)として算出しています。測定対象は主に好気性及び通性嫌気性の中温性菌です。したがって、もし、この条件下で生育しうる食中毒菌が存在する場合は、一般細菌数(生菌数)として測り込まれます。
- 大腸菌群の定義は何ですか。
「大腸菌群」は、グラム陰性の無芽胞桿菌で35℃、48時間以内に乳糖を分解して酸とガスを産生する好気性または通性嫌気性菌(食品衛生検査指針 微生物編)と定義されています。糞便あるいは腸管系病原菌の汚染指標として最も一般的に試験されています。
しかし、大腸菌群は自然界に広く分布することから、今日では従来の安全性(糞便汚染)の指標というよりは、環境衛生管理上の衛生指標菌と考えられています。
- 大腸菌群が陽性になってしまいました。衛生管理が良くなかったのでしょうか。
大腸菌群は自然界に広く分布しているので、検出されたことが、そのまま糞便汚染や腸管系病原菌(サルモネラ、腸管出血性大腸菌O157、赤痢菌等)の存在を意味するわけではありません。ただし、加熱済みの食品から検出した場合は、不適切な加熱処理や加熱後の二次汚染等を疑う必要があります。
糞便由来かどうかを確認するのであれば大腸菌の試験を行うことも考えられます。なお、未加熱品の糞便汚染の確認には、大腸菌の試験を行う方が適当です。
- MPN算出法とはどのような方法ですか。
MPN はMost Probable Numberの略で、「最確数」と訳されています。
食品中に存在する微生物の生菌数を測定する試験(定量的試験)では、寒天培地を用いる方法(集落計数法)と液体培地を用いる方法(MPN算出法)が広く知られています。 MPN算出法は、検体の連続希釈液を3本又は5本ずつの液体培地(試験管)に接種培養して「陽性」と なった試験管数の出現率から生菌数(検体中の菌数の最も確からしい数値)を確率論的に推計する方法です。最確数を算出する際に使用するのが「最確数表」 で、最確数表には各陽性管数の組み合わせに対する最確数が記載されています。
通常、集落計数法における検出限界が10/g(1/ml)であるのに対して、MPN算出法(試験管数が3本ずつの場合)では30/100g(3/100ml)となります。従って、MPN算出法ではより少ない生菌数を推計することができます。
- 一般細菌数(生菌数)の結果300以下/gとは何ですか。
検体1g中の菌数が、300個以下であることを表しています。
通常、生菌数は1平板の菌数が30から300に入る集落数に希釈倍数を乗じて算出しています。しかしながら、すべての平板の菌数が30未満の場合には、検出限界である30に最も低い希釈倍数を乗じて、「300以下/g」または「30以下/ml」と記載しています。これは食品衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」及び「食品、添加物等の規格基準」の氷雪の項目に規定されている生菌数の測定法によっています。
- 大腸菌群の結果「陰性/2.22g」「陰性/0.1g」とは何ですか。
2.22gや0.1gは、検体量を示します。
試験方法によって使用する検体量が異なります。「陰性/2.22g」とは、BGLB法において、2.22g当たりの検査で大腸菌群が陰性であったことを意味します。2.22gとなる理由は次のとおりです。検査ではまず始めに検体の10倍希釈試料液を調製します。続いて、その10倍希釈試料液から10ml、1ml、0.1mlずつを各2本のブイヨン発酵管に接種して試験します。つまり、すべての接種量を合計すると10倍希釈試料液22.2ml当たりとなり、これは検体2.22gに相当します。 ただし、陽性時には、10倍希釈試料液から10ml(検体1g相当)、1ml(検体0.1g相当)、0.1ml(検体0.01g)のどの段階まで陽性であったかを結果としてあらわします。つまり、「陽性/1g」、「陽性/0.1g」、「陽性/0.01g」のいずれかの結果になります。
「陰性/0.1g」は、デソキシコレート寒天平板培養法において大腸菌群が検出されなかった場合になります。10倍希釈試料液1mlを試験し、これが検体0.1gに相当します。
食品の品質管理(規格等)
- 酸価、過酸化物価とはどういうものですか。
食品に含まれる油脂が、空気中の酸素により酸化し、生成した過酸化脂質の量を測定するのが過酸化物価(POVと略記されることが多い)です。したがって、油脂の酸化の度合いを直接示します。
一方、酸価(AVと略記されることが多い)は、過酸化物価で測定しているものとは異なり、含まれる油脂中の遊離脂肪酸の量を表します。遊離脂肪酸は、油脂が劣化するなどにより、油脂の加水分解が起きて生じます(油脂が遊離脂肪酸の形に変わります)。食品中の油の劣化の程度を知るには、酸価と過酸化物価の併用が多いようです。
酸価は、試料1g中に含まれている遊離脂肪酸を中和するのに要する水酸化カリウムの㎎数をいいます。
過酸化物価は、規定の方法に基づき、試料にヨウ化カリウムを加えた場合に遊離されるヨウ素を、試料1kgに対するミリ当量数で表したものをいいます。酸価に単位はありません。
過酸化物価は、「meq/kg」(ミリイクイバレントパーキログラム) で表します。(参考:基準油脂分析試験法)
- 重金属(Pbとして)では何を測定しているのですか。どのような場合に測定するのですか。
「重金属(Pbとして)」と表現される試験項目は、硫化ナトリウム比色法で試験した場合です。この試験法で有色の硫化物を作るのは、Pb、Cu、Cd、Bi、Sn(スズ)等で、最も感度が高いのは(呈色の強いのは)PbとCuです。
「重金属(Pbとして)」の試験項目は、①検出されないことの確認をしておきたい場合、②どのレベルか調べておきたい場合、③規格試験を用途とした場合には適当です。検出されて、含有する元素を特定しようとする場合、又はヒ素(As2O3として)、鉛、カドミウム、総水銀等のように危害性の含有が予測される場合は、個々の元素の分析をお勧めします。(食品添加物の「重金属(Pbとして)」の規格は20ppm(20μg/g)の例があります。)
- 酸価、過酸化物価について定められている規格基準はありますか。結果の評価はどのようになりますか。
食品衛生法では、酸価、過酸化物価とも抽出油についての規格基準が定められています。即席めん類(めんを油脂で処理したものが対象)は酸価が 3を超え、又は過酸化物価が 30を超えるものであってはならないとされています。
別に厚生労働省の通知文書「菓子の製造・取
り扱いに関する衛生上の指導について」に「油脂で処理した菓子(油脂分を粗脂肪として10 %(重量%)以上含むもの)」の規格があります。製品に含まれる油脂の酸価が3を超え、かつ過酸化物価が30を超えるものであってはならないこと,及び酸価が5を超え、又は過酸化物価が50を超えるものであってはならないことと定められています。
- 合成樹脂の規格試験において、「厚生省告示第370号」という場合と「厚生省告示第201号」がありますが、どう違うのですか。
基本になっている規格は「食品、食品添加物等の規格基準」(昭和34年の厚生省告示第370号)で、これは毎年のように一部改正されています。 一般に201号と呼ばれているのは平成18年の厚生労働省告示第201号のことで、食品、添加物、器具及び容器包装、おもちゃ等の規格基準の一部改正・追加の告示です。
改正には、それぞれ告示の番号が付いていますが、法律としては元になる規格である370号に溶け込むという解釈になっています。
201号は大きな改正なので201号と呼ばれていますが、201号規格という表現は俗称であり、201号で改正されたというだけであって、370号が廃止されて新しい法律にならない限り、370号が正式な番号になります。古くは20号規格(昭和57年)と呼ばれたこともありましたが、これも同様です。
セミナー(有料)関連
- 修了証をなくしました。再発行できますか。
可能です。ただし事務手数料として実費(税別 2,000円)を申し受けます。
- HACCPセミナーを受講したいのですが。
こちらをご覧ください。開催予定のコース一覧をお示ししています。コース名をクリックすれば開催日程,会場等の詳細を確認いただけます。
- どのコースを選択すれば良いですか。
こちらをご覧ください。コース名をクリックするといずれのコースもコースコンセプトや対象者を確認いただけます。さらに詳細をお知りになりたい場合はこちらのお問い合わせページで「テクニカルセミナー(有料のセミナー)に関するお問い合わせ」をご利用ください。担当から折り返しの連絡をいたします。
- 各コースの空き状況はどうしたら分かりますか。
こちらから確認いただけます。ご希望のコース名をクリックすると開催回ごとの状況を確認いただけます。すでに満席になっている場合はこちらから空席待ちいただくことも可能です。
- 請求書が届いていないようです。
従前は該当するコースの開催が確定した時点で請求書を発行しておりましたが,インボイス制度において請求書に納品日の記載が必要になったことを受けて現在は当該コースの開催日以降に発行しております。
- セミナーを修了したら名刺に資格として何か書けますか。
特に制約は設けていません。名刺やプロフィールに「日本食品分析センター HACCP ○○コース修了」と記載されている事例もあります。